水耕栽培は土を使わず水と液体肥料で植物を育てる方法で、室内でも手軽に野菜やハーブなどを育てられるため、近年とても人気があります。
しかし、育てているうちに葉が黄色くなってしまうという経験をした方もいるかもしれません。

葉が黄色くなるのは、水耕栽培でよくあるトラブルの一つです。
原因を理解し適切に対処すれば、植物は再び元気を取り戻します。
この記事では、水耕栽培で葉が黄色くなる主な原因と、その対策について初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
水耕栽培で葉が黄色くなる主な原因

水耕栽培で葉が黄色くなる原因はいくつか考えられます。
それぞれの原因によって葉の黄くなり方や植物の状態も異なるため、しっかりと原因を見極めることが大切です。
ここでは、主な原因を5つに分けて解説していきます。
- 栄養不足
- 根腐れ
- 水質の問題
- 日照不足
- 病害虫
これらの原因を理解することで、葉が黄色くなった際に適切な対処ができるようになります。
原因①:栄養不足
植物が生長するためには、窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)をはじめとする様々な栄養素が必要です。
これらの栄養素は、植物の葉緑素の生成や光合成、根の発達などに重要な役割を果たしています。
水耕栽培では、土壌栽培と異なり、水に溶けた液体肥料から栄養を吸収します。
そのため、液体肥料の濃度が薄すぎたり、必要な栄養素が不足していると、葉が黄色くなってしまうことがあります。
全体的に葉が薄黄色くなる場合
全体的に葉の色が薄くなり、生育も緩慢になる場合は、窒素不足の可能性が高いです。
窒素は葉緑素の生成に不可欠な要素であるため、不足すると葉の色が薄くなってしまいます。
葉脈は緑色で葉肉が黄色くなる場合
葉脈は緑色を保ちながら、葉肉の部分だけが黄色くなる場合は、鉄不足の可能性があります。
鉄は葉緑素の生成に関与しており、不足すると葉肉部分の葉緑素が生成されにくくなります。
原因②:根腐れ
根腐れは、根が酸素不足によって呼吸できなくなり、腐ってしまう状態です。
水耕栽培では、水に浸かっている根に十分な酸素が供給されないと根腐れを起こしやすくなります。
根腐れの原因としては、水のやりすぎ、水換え不足、容器内の通気性の悪さなどが挙げられます。
根の状態
根腐れを起こした根は、茶色く変色したり、ぬめりがあったり、悪臭を放ったりします。
健康な根は白く、ハリがあります。
葉への影響
根が腐ってしまうと、水分や栄養を十分に吸収できなくなります。
そのため、葉が黄色くなったり、しおれたりします。
原因③:水質の問題
水耕栽培では、水のpH(酸性・アルカリ性の度合い)が植物の生育に大きく影響します。
植物の種類によって適正なpHは異なりますが、一般的には弱酸性(pH5.5~6.5程度)が適しています。
pHが大きく偏ると、栄養素の吸収が阻害され、葉が黄色くなる原因となります。
また、水温も重要です。
水温が高すぎると根腐れの原因になったり、水中の酸素量が減少し、植物の生育に悪影響を与えます。
原因④:日照不足
植物は光合成によって栄養を作り出しています。
そのため、十分な日光が当たらないと、葉緑素が十分に生成されず、葉が黄色くなることがあります。
特に、日照時間が短い冬場や、日当たりの悪い場所で栽培している場合は、日照不足に注意が必要です。
原因⑤:病害虫
水耕栽培でも、病気や害虫の被害を受けることがあります。
特に、カビや細菌による病気や、アブラムシなどの害虫は、葉を黄色くしたり、生育を阻害したりする原因となります。
葉が黄色くなった時の対策
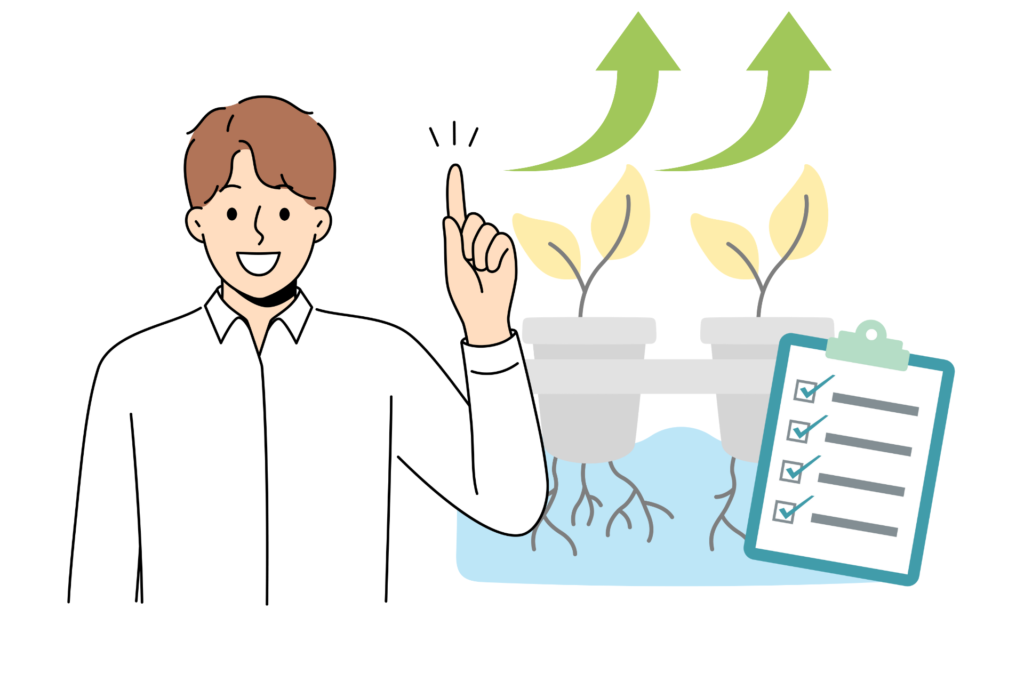
葉が黄色くなる原因が分かったら、適切な対策を行うことで植物を回復させることができます。
ここでは、先ほど解説した原因別に、具体的な対策方法を説明していきます。
- 栄養不足の場合
- 根腐れの場合
- 水質の問題の場合
- 日照不足の場合
- 病害虫の場合
症状が重い場合は、回復までに時間がかかる場合もあります。
諦めずに、根気強くケアを続けることが大切です。
対策①:栄養不足の場合
栄養不足が原因で葉が黄色くなっている場合は、適切な肥料を与えることが重要です。
液体肥料の種類
水耕栽培には、液体肥料が適しています。
液体肥料には、植物の生育に必要な栄養素がバランス良く含まれている総合液体肥料と、特定の栄養素を補うための単肥があります。
初心者の方は、まず一般的な総合液体肥料を使用することをおすすめします。
液体肥料の使い方
液体肥料は、必ず水で希釈してから使用します。
希釈倍率は、肥料の種類や植物の種類によって異なりますので、製品の説明書をよく読んでください。
一般的には、500倍~1000倍程度に希釈することが多いです。
肥料を与える頻度
肥料を与える頻度は、植物の種類や生育状況によって異なりますが、一般的には、1週間に1回程度を目安にします。
生育が旺盛な時期は、少し頻度を増やしても良いでしょう。
ただし、与えすぎは逆効果になるため、注意が必要です。
葉面散布
葉面散布は、液体肥料を葉に直接散布する方法です。
根からの吸収が弱っている場合や、速効性を期待する場合に有効です。
ただし、葉に水滴が残ると病気の原因になることがあるため、風通しの良い時間帯に行い、水滴を拭き取るようにしましょう。
対策②:根腐れの場合
根腐れが原因で葉が黄色くなっている場合は、早急な対応が必要です。
まず、植物を容器から取り出し、傷んだ根(茶色く変色したり、ぬめりがある根)を清潔なハサミで切り取ります。
容器と培地の洗浄
容器と培地(ハイドロボールなどを使用している場合)をよく洗浄します。
特に、容器はカビや細菌が繁殖している可能性があるため、漂白剤などで消毒すると効果的です。
水の交換
新しい水に交換します。
この際、根腐れ防止剤などを添加すると、再発を予防することができます。
通気性の確保
根に十分な酸素が供給されるように、容器の底に空気の通り道を作ったり、エアレーション(水中に空気を送り込むこと)を行ったりするなどの対策を行います。
対策③:水質の問題の場合
水質が原因で葉が黄色くなっている場合は、水のpHを調整することが重要です。
pH測定器などを使用して、水のpHを測定します。
pH調整
pHが高すぎる場合は、pH調整剤(酸性)を使用してpHを下げます。
逆に、pHが低すぎる場合は、pH調整剤(アルカリ性)を使用してpHを上げます。
pH調整剤を使用する際は、少しずつ加えて、こまめにpHを測定しながら調整するようにしましょう。
水の交換
定期的に水を交換することで、水質の悪化を防ぐことができます。
対策④:日照不足の場合
日照不足が原因で葉が黄色くなっている場合は、日当たりの良い場所に移動するか、植物育成ライトを使用します。
日当たりの良い場所への移動
できるだけ日当たりの良い場所に移動させます。
ただし、急に直射日光に当てると葉焼けを起こすことがあるため、徐々に日光に慣らすようにしましょう。
植物育成ライトの使用
日照時間が短い場合や、日当たりの悪い場所で栽培している場合は、植物育成ライトを使用すると効果的です。
植物育成ライトには、様々な種類がありますので、育てる植物に合ったものを選びましょう。
対策⑤:病害虫の場合
病害虫が原因で葉が黄色くなっている場合は、適切な農薬や駆除方法を使用します。
農薬の使用
病気の種類や害虫の種類によって、効果のある農薬が異なります。
製品の説明書をよく読んで、適切な農薬を使用するようにしましょう。
手作業での駆除
アブラムシなどの害虫は、手作業で取り除くこともできます。
早期発見と予防
病害虫の被害を最小限に抑えるためには、早期発見と予防が重要です。
日頃から植物の状態をよく観察し、異常があれば早めに対処するようにしましょう。
予防策

葉が黄色くなる原因と対策について解説してきましたが、何よりも大切なのは日頃からの予防です。
適切な管理を行うことで、葉の黄化を未然に防ぎ、植物を健康に育てることができます。
ここでは、水耕栽培で葉が黄色くなるのを防ぐための具体的な予防策をご紹介します。
- 定期的な水換え
- 適切な肥料管理
- 十分な日照と適切な温度管理
- 風通しの確保
- 定期的な観察
- 清潔な環境の維持
これらの予防策を実践し、葉が黄色くなるリスクを減らしましょう。
特に、日々の観察と適切な管理が、植物の健康を維持する上で重要です。
予防①:定期的な水換え
水耕栽培では、水が汚れてくると水質が悪化し、根腐れや病気の原因となります。
そのため、定期的な水換えが非常に重要です。
水換えの頻度
水換えの頻度は、植物の種類や生育状況、容器の大きさなどによって異なりますが、一般的には、夏場は2~3日に1回、冬場は1週間に1回程度を目安にします。
水換えの方法
水換えをする際は、古い水を完全に捨て、新しい水に交換します。
この際、容器や培地も軽くすすぐと、より清潔に保つことができます。
予防②:適切な肥料管理
肥料の与えすぎや不足は、葉の黄化の原因となります。
適切な肥料管理を心がけましょう。
肥料の濃度
肥料を与える際は、必ず希釈倍率を守り、適切な濃度で使用します。
濃すぎる肥料は、根を傷める原因となります。
肥料を与えるタイミング
肥料を与えるタイミングは、植物の生育状況に合わせて調整します。
生育が旺盛な時期は、少し多めに与えても良いですが、休眠期や生育が緩慢な時期は、控えめにします。
定期的な水質測定
pH測定器やpH試験薬を使用して、定期的に水質のpHを測定し、適切な範囲に保つようにします。
予防③:十分な日照と適切な温度管理
植物は光合成によって栄養を作り出しているため、十分な日光が必要です。
また、適切な温度も生育に大きく影響します。
日照時間の確保
できるだけ日当たりの良い場所に置き、十分な日照時間を確保します。
日照不足の場合は、植物育成ライトの使用を検討しましょう。
適切な温度管理
植物の種類によって適正な温度は異なりますが、極端な高温や低温は避けるようにします。
予防④:風通しの確保
風通しが悪いと、湿度が高くなり、カビや病気の原因となります。
定期的に窓を開けて換気を行い、室内の空気を入れ替えます。
必要に応じて、サーキュレーターなどを使用して、空気を循環させると良いです。
予防⑤:定期的な観察
日頃から植物の状態をよく観察することで、異変を早期に発見することができます。
葉の色や状態、根の状態などを定期的にチェックし、異変があれば早めに対処するようにします。
また、害虫が発生していないかも、チェックしましょう。発見した場合は、早めに駆除するようにします。
予防⑥:清潔な環境の維持
容器や培地、周囲の環境を清潔に保つことで、病気の発生を抑えることができます。
定期的に容器を洗浄し、カビや細菌の繁殖を防ぎます。
培地(ハイドロボールなど)を使用している場合は、定期的に交換することで、清潔な状態を保つことができます。
まとめ
この記事では、水耕栽培で葉が黄色くなる主な原因とその対策、そして日頃からできる予防策について詳しく解説してきました。
葉が黄色くなる原因は、
- 栄養不足
- 根腐れ
- 水質の問題
- 日照不足
- 病害虫
など様々ですが、それぞれの原因に適切な対処を行うことで、植物は再び元気を取り戻す可能性があります。
特に重要なのは、日頃からの予防です。
- 定期的な水換え
- 適切な肥料管理
- 十分な日照と適切な温度管理
- 風通しの確保
そして何よりも大切な定期的な観察を心がけることで、葉の黄化を未然に防ぎ、健康な植物を育てることができます。
水耕栽培は、土を使わずに手軽に植物を育てられる魅力的な方法です。
葉が黄色くなってしまうと心配になるかもしれませんが、この記事でご紹介した原因と対策を参考に、落ち着いて対処してみてください。
大切なのは、植物の状態をよく観察し、早めに対処することです。
もし葉が黄色くなっても、諦めずに適切なケアを続ければ、多くの場合は回復します。
植物の成長を間近で見守り、愛情を込めて育てることで、水耕栽培の楽しさをより深く味わうことができるでしょう。
この記事が、皆様の水耕栽培ライフのお役に立てれば幸いです。



コメント